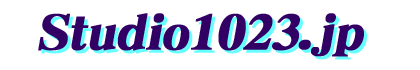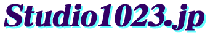本棚1段分のレイアウト

スチール製本棚に入替運転もできるレイアウトが欲しくなり、電源・コントロールボードを内蔵させ洗浄線・ホーム・車庫のあるレイアウトセクション(最近この言い方はしない?)を作りました。
…と言っても着工は40年近く前の事です。
 線路配置は左から斜めに本線が入り、島式ホームの2線どちらかに入線、どちらからも洗浄線には移動でき奥の2番線からは車庫線にも転線できます。
線路配置は左から斜めに本線が入り、島式ホームの2線どちらかに入線、どちらからも洗浄線には移動でき奥の2番線からは車庫線にも転線できます。
奥には留置線(通電可)もあり、構内を左右に移動できるパズルのような配線にしました。
 手前に内蔵したコントロールボードは、小学生の時に作ったNゲージ初代レイアウトの制御機器(半世紀以上前の3アンペアトランスとセレン整流器・100オームレオスタットによる抵抗制御)を流用、アルミ板を加工したパネルに白テープで線路配置を表示、ポイントは黒・赤(ずいぶん色褪せた)の押しボタンはポイント切替、ブロックごとににスイッチを付け一部分だけ動かすこともできます。
手前に内蔵したコントロールボードは、小学生の時に作ったNゲージ初代レイアウトの制御機器(半世紀以上前の3アンペアトランスとセレン整流器・100オームレオスタットによる抵抗制御)を流用、アルミ板を加工したパネルに白テープで線路配置を表示、ポイントは黒・赤(ずいぶん色褪せた)の押しボタンはポイント切替、ブロックごとににスイッチを付け一部分だけ動かすこともできます。
 右側には1面2線のプラットホームがあり改札口へは構内踏切を渡るタイプです。
右側には1面2線のプラットホームがあり改札口へは構内踏切を渡るタイプです。
駅前広場の端はバス乗り場で、バスは職員の誘導でバックで入ります。
 左側には丸い屋根の検修庫と洗浄線、手前は乗務員詰所・奥は洗浄員の詰め所です。
左側には丸い屋根の検修庫と洗浄線、手前は乗務員詰所・奥は洗浄員の詰め所です。
洗浄係の詰め所はホーム用のパーツを改造し屋根を付けましたが、保線用も含め詰所はすべて形が違います。
 中央手前には変電所その左側が本線です。
中央手前には変電所その左側が本線です。
 作り始めた頃は建物はGM製品しか無く、それらの組立・加工・改造で全体の風景を作っています。
作り始めた頃は建物はGM製品しか無く、それらの組立・加工・改造で全体の風景を作っています。
駅舎は改札の向きを変え、駅前には売店・青い屋根は交番のつもりでポストや公衆電話も見えます。

横向きにした改札口から線路を渡ってホームです。
変電所との間には古めの木造トイレがありますが早くきれいに建て替えた方が…
奥の線路には保線車両を止めるにはぴったりです。
 検修庫とホーム屋根裏には昔ながらの電球による照明を入れています。
検修庫とホーム屋根裏には昔ながらの電球による照明を入れています。
 深夜のホームといった感じです。
深夜のホームといった感じです。
 検修庫は細かい窓桟の影がきれいな模様になります。
検修庫は細かい窓桟の影がきれいな模様になります。